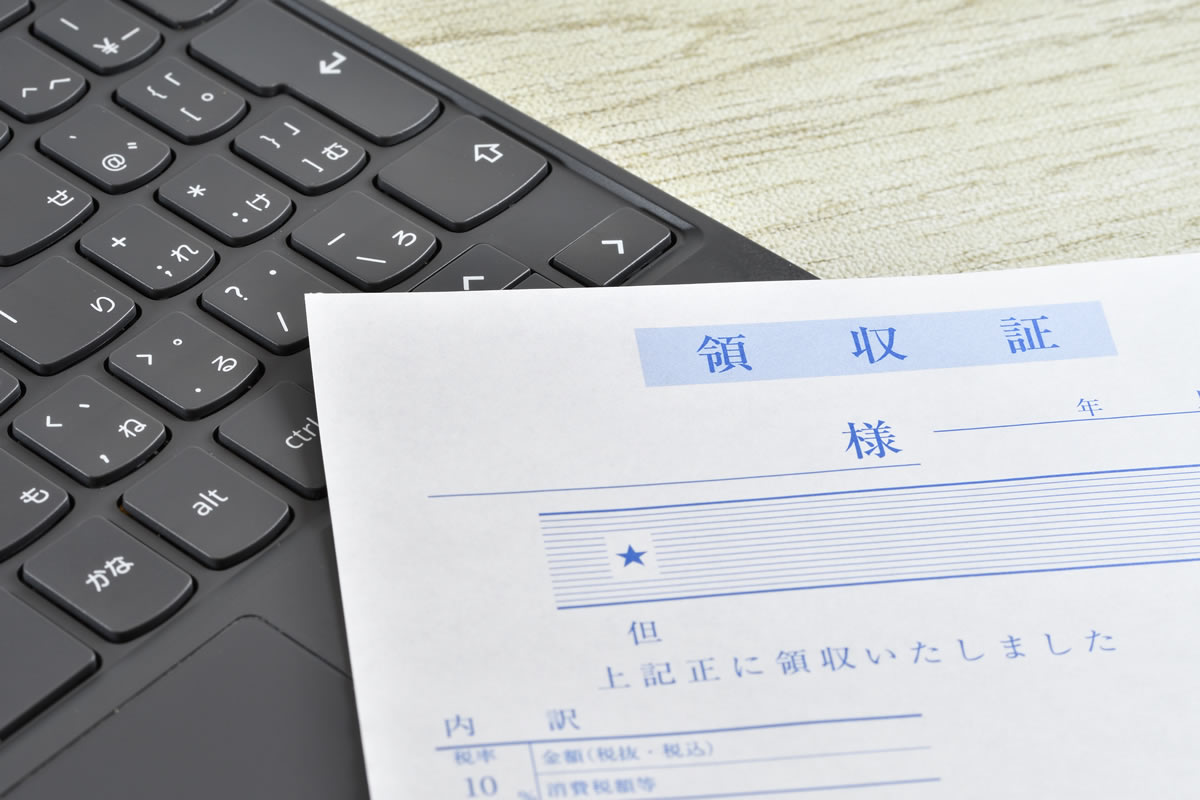クロノス広報チーム
企業が使用する建物やPCなどの機械、車などの資産は、長く使用するうちに少しずつ価値が下がっていきます。
資産を取得した際に全額を費用にするのではなく、耐用年数(資産の使用期間)で定められた年数で分割し、計上していくのが減価償却の考え方です。
本記事では、減価償却費のそれぞれ意味や目的、計算方法、注意点などについてわかりやすく解説していきます。
勤怠管理システムについて無料で見積もり・相談できます無料でお問い合わせ
減価償却とは
減価償却費(げんかしょうきゃくひ)とは、経費の勘定科目の一種です。
取得した建物やPCなどの機械、車など会社にとっての資産は長く使用するものと考え、使用するうちに価値は減少するものとなるため、取得した費用を資産ごとに異なる耐用年数にあわせて分割し、毎月減価償却費として複数年に分割して計上していくことを指します。
また、ここでいう資産とは減価償却資産とも呼ばれ、中小企業の場合は長期に渡って使用する30万円以上の費用が基本的には対象となります。
一方で減価償却できない費用もあります。例えば消耗品のような1年未満で使い切ってしまう物や10万円未満で取得したものは減価償却ではなく取得した時点で消耗品費として計上するため、対象には含まれません。いくらからが減価償却の対象となるのか注意が必要です。
長く使用するものか価値が下がるものかどうかという点が、減価償却のポイントです。
減価償却費を計上する目的
減価償却費を計上する目的は、資産を取得した費用をその資産が働いている期間に合わせて分配することで、各期の利益を正しく表すことです。
一定の期間において収益を生み出すため必要となった費用のみを計上するため、財務諸表を正確かつ透明性のあるものとして扱うことができます。
また、減価償却は資産の老朽化や更新に備えながら利益のアンバランスをならす効果や、現金支出を伴わない費用でありながら財務上は損金として扱われるため、課税される所得を抑えることにもつながります。
このように、減価償却は会計と財務両面で重要な役割を果たすため、資産の基準に応じて最適な償却方法を選択し、資金管理に役立てたせることができるのです。
減価償却費を計上しないとどうなる?
法人に関しては減価償却費を行わない場合でも法律上の問題はありません。
しかし、計上しない場合は資産が古くなっても帳簿上は全額のままとなるため、実際の価値の減少は反映されず、その結果、経費が少なく計上されるため利益が過大に算出され、法人税が増えてしまいます。
また、金融機関からは資金を多く見せ、利益を操作しているのではないかと受け取られる可能性も考えられます。
減価償却は、個人事業主の場合、法人の場合で取り扱いが異なるためそれらを理解したうえで適切の計上することが必要です。
- 個人事業主
強制償却が原則となります。
取得した資産については、減価償却費を計上しなければ必要経費と認められません。 - 法人
任意償却が認められています。
計上しない場合は利益が増えることで課税額も増えるため、法人税が増加することに注意が必要です。
減価償却費として計上できる資産・できない資産
すべての固定資産が減価償却の対象となるわけではなく、行うべき資産とそうでない資産があります。
適用となる対象はどのような固定資産となるのか、主な例を以下に挙げていきます。
減価償却費として計上できる資産
減価償却費として計上できる資産の条件は、以下の通りとなります。
- ・ 事業用に使用されること
- ・ 使用期間が1年以上で取得費用が10万円以上であること
- ・ 使用するうちに価値が減少するもの
また、固定資産には有形であるか無形であるかなどの違いがあり、主に次の種類に分けられます。
有形固定資産
簡単に言うと、目に見える物理的な資産を指します。
| 建物 | オフィスビル、店舗、工場、倉庫など |
|---|---|
| 土地 | オフィスビル、駐車場、資材置き場、社宅敷地など |
| 機械装置 | コンピューター、プリンター、製造機器設備など |
| 車両運搬具 | 営業車、バス、トラック、漁船など |
無形固定資産
物理的な実体をもたない、使用価値や権利などの資産を指します。
- ・ ソフトウェア
- ・ 特許権
- ・ 商標権
- ・ 借地権
- ・ のれん
- ・ 育成権
- ・ 漁業権
- ・ 水利権 など
生物
観賞用や興行用などに該当するものを除く、事業の生産活動に用いられる生きた資産を指します。
| 育成中の果樹 |
耐用年数に従い、収支相償うに至ると認められる樹齢で減価償却を行います。 取得価額=出産費、種付費、出産費、飼料費、労務費、経費などを合計した金額 |
畜産動物 |
耐用年数に従い、業務の用に供するに至った年齢で減価償却を行います。 取得価額=種苗費、肥料費、労務費、経費を合計した金額 |
|---|
減価償却費として計上できない資産
一方で、減価償却費として計上できない資産には、使用や経年によって価値が減少しないもの、またはその価値の減少を合理的に見積もれないものが含まれます。 計上できない資産の条件は以下のとおりです。
- ・ 個人的利用など業務用に供していない資産
- ・ 使用期間が1年未満で取得費用が10万円以下である
- ・ 使用や時間が経過しても価値が減少しないもの
- ・ 取得費用が不明または算定困難な資産
具体的には、オフィスビルの敷地(=土地)は、建物とは異なり時間が経っても価値が減らないため減価償却費として計上することはできません。
また、絵画や彫刻などの美術品は一般的に長期間にわたり価値が減少しないことが明らかなものは減価償却の対象となりません。
しかし、1点100万円以上か未満かによって対象となる場合もあるため注意が必要です。
このように、減価償却の対象外となるかどうかは「価値が減少するか」「業務に使用する資産か」を押さえることがポイントです。
減価償却費に関連する用語
次に、減価償却を知るうえで必要となる勘定科目などの専門用語について解説していきます。
減価償却
減価償却とは、企業が使用する資産を長く使用するものと考え、耐用年数で定められた年数で分割し、毎月減価償却費として複数年に分割して計上していくことを指します。 取得時に全額を経費にせず、使用年数に応じて少しずつ費用化していくのが減価償却です。
減価償却累計額
減価償却累計額とは、これまでに計上された減価償却費の総額を示す勘定科目となります。
減価償却とは、企業が使用する資産を耐用年数にあわせて分割し、計上していくことであると前述しました。この減価償却に関わる費用の仕訳方法には、主に「直接法」「間接法」の2種類があります。
直接法
減価償却費を計上する際に、固定資産から直接差し引く方法です。
固定資産の帳簿価額が毎年減少されるため、帳簿上で「今いくらの価値が残っているのか」がわかりやすくなる一方、原価は把握しづらくなります。
間接法
減価償却費を「減価償却累計額」で計上し、固定資産から間接的に差し引く方法です。 資産の取得原価をそのまま残すことができるため、原価と償却額を同時に把握できます。
一般的には、資産の取得価額を明確に残せる間接法が多く採用されています。
少額減価償却資産
少額減価償却資産とは、次のいずれかに該当するものを指します。
- ・ 使用可能期間が1年未満の資産
- ・ 取得価額が10万円未満のもの
中小企業などを対象に、取得価額30万円未満(中小企業の場合は特例で30万円未満または20万円未満)であれば、取得年度に全額を一括して損金または経費として計上できる少額減価償却資産の特例も存在します。
この特例で対象となるのは、中小企業または農業協同組合などで青色申告をする法人のうち、従業員数が500名以下であること、事業年度開始の時の資本金または出資金の額が1億円以下の法人が対象です。
少額減価償却資産の特例が適応されるのは、2026年3月31日までの間に取得した減価償却資産のみが対象となるため注意しましょう。
参考:No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示|国税庁
参考:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁
耐用年数
耐用年数とは、資産が経済的に使用可能と見込まれる期間を指し、その期間にわたって取得原価を減価償却費として配分するための基準となります。
税法上の耐用年数は、主に法人税法や所得税法に基づき、資産の種類ごとに法定で定められた耐用年数です。例えば建物や機械、車両など、資産の分類ごとに標準的な耐用年数が規定されており、企業はこれに従って減価償却費を計算します。
一方、国際財務報告基準(IFRS)では、耐用年数は「資産が企業の使用により経済的利益を生み出す期間」として企業が合理的に見積もる必要があります。 つまり、財務報告に関する原則を明確にし、企業に具体的な運用は任せるという方法です。
資金調達の手段が多様化するメリットがあるものの、この方法はグローバルな基準を持つことから一般的には耐用年数に従って減価償却を行っている企業が多いといえます。
減価償却資産の耐用年数は資産によって大きく変わるため、耐用年数表を参考にしてみてください。
事業供用日
事業供用日とは、取得した固定資産を実際に事業で使用し始めた日を指します。 減価償却費の計算は、この日を起算日として行われるという点がポイントです。
具体例としては、工場の機械が稼働を開始した日や、社用車を業務で初めて運行した日が該当し、建物の場合は完成し引き渡しを受けて業務に使用可能となった日が事業供用日となります。
税務上も事業供用日から減価償却費の計算を開始するため、取得日や納品日ではなく、実際に使用開始した日を正確に把握することが重要です。
減価償却費の計算方法
減価償却について解説してきましたが、では実際にどのように計算すればよいのでしょうか。 減価償却の主な計算方法は主に2つ、「定額法」と「定率法」があります。 他にも「生産高比率法」「リース期間定額法」といった計算方法もあるため、それらについて説明していきます。
「定額法」での計算方法
定額法とは、毎年定額の減価償却費を計上することを指します。 一定の額を計上するだけなので、計算も非常にシンプルでわかりやすいのが特徴です。
計算式は以下のようになります。
▼定額法の計算式
減価償却費=取得価額×定額法の償却率
▼計算例
オフィスビルの取得価額2億円、耐用年数50年の減価償却対象となる資産を取得した場合、 償却率は0.02%となるため以下の計算方法で求められます。
2億(取得価額)×0.02(定額法の償却率)=400万円(減価償却費)
毎月400万円を計上していきますが、定額法で減価償却を行う場合は、耐用年数最後の事業年度で1円差し引く必要があるため最後の50年目は3,999,999円で計上します。
耐用年数で定められた一定の償却率を使用して計上する方法となるため、初期に大きな費用が発生せず、長期的な資金計画が立てやすいことや経営上の見通しを安定させやすい点がメリットといえます。
一方で、資産の実際の使用状況や価値の減少スピードに差がある場合には、実態と費用配分が一致しにくいというデメリットもあります。
計算がシンプルでわかりやすく、税務・会計の両面で最も広く採用されている償却方法です。
「定率法」での計算方法
定率法とは、毎年一定の割合で計上することを指します。 計上額は徐々に減少していきますが、初年度の償却額が大きくなります。
事業供用日直後は資産の効率や価値が高く、経済的利益を多く生むと考えられるためその実態に合わせて初期に償却費を多く計上できるのが特徴です。
計算式は以下のようになります。
▼定率法の計算式
減価償却費=(取得価額-過去の減価償却費を差し引いた取得価額)×定率法の償却率
減価償却資産の取得価額は2億円、耐用年数50年の減価償却対象となる資産を期首に取得した場合、償却率は0.046%となり、以下の計算方法で求められます。
<1年目>
(2億(取得価額)-0(過去の減価償却費を差し引いた取得価額)×0.046(定率法の償却率)=920万円(減価償却費)
<2年目>
(2億円(取得価額)-920万(過去の減価償却費を差し引いた取得価額)×0.046(定率法の償却率)=877.7万円(減価償却費)
<3年目>
(2億(取得価額)-920万-877.7万(過去の減価償却費を差し引いた取得価額)×0.046(定率法の償却率)=837.7万円(減価償却費)
定額法では毎月一定額を計上しますが、定率法ではその年の期首時点の残高(過去の償却費を差し引いた額)に償却率をかけ、毎年少しずつ計上していきます。 初年度に大きく計上することで節税効果が早期に得られるメリットもありますが、後期になると償却費が少なくなるため年度ごとの費用はばらつきが生じます。
「生産高比例法」での計算方法
生産高比例法とは、実際の利用料に応じて減価償却費を計上することを指します。 実際の利用状況と費用負担を一致させられる点にありますが、利用や稼働量が多い年度ほど償却費が増え、少ない年度は減るといった特徴があります。
計算式は以下のようになります。
▼生産高比例法の計算式
減価償却費=取得価額×(実際生産高÷見積総生産高)
配分する際には生産高を使う減価償却の方法となるため、対象は生産高が明確に計算できる固定資産かどうかがポイントです。
資産の稼働実績に基づいて合理的に費用配分できることが特徴で、収益と費用の対応関係を明確にできるといったメリットがあります。
一方で、生産高の実績を毎期把握する必要があるため、計算や記録管理の手間がかかるというデメリットもあります。それでも実際の利用度合いに応じた償却が可能なため、生産性重視の設備管理に向いている方法といえるでしょう。
「リース期間定額法」での計算方法
リース期間定額法は、リース資産の取得価額をリース期間で均等に減価償却費を計上することを指します。
期間内に一定の額を計上するため、毎期同額の費用を計上できため損益計算を安定させやすく、費用配分が明確でわかりやすいのが特徴です。
▼リース期間定額法の計算式
減価償却費(償却限度額)=(リース資産の取得価額-残価保証額)÷リース期間の月数×当期におけるリース期間の月数
この方法は、ファイナンスリース取引において適用されることが多く、リース契約期間を耐用年数とみなして計算します。たとえば、60万円のリース資産を3年間使用する場合、毎期20万円ずつ償却します。
また、このファイナンスリース取引には2つの方法の取引があることも押さえておきましょう。
- ・ 所有権移転外リース:リース期間が過ぎたら所有者に返すもの
- ・ 所有権移転リース :リース後または途中で所有権が譲渡されるもの
定率法と比較すると初期費用をリースによって平準化することができるため、適切な損益の費用計上をできる点がメリットといえるでしょう。
減価償却費の仕訳方法
減価償却に仕訳方法には大きくわけて2つ、「直接法」と「間接法」があります。
どのような勘定科目を使用して仕訳していくのか、特徴について解説していきます。
「直接法」での仕訳方法
直接法は減価償却費を計上する際に、固定資産から直接差し引いて帳簿価額を表示させる方法となります。借方に減価償却費、貸方に固定資産の勘定科目を使用することが特徴といえるでしょう。
固定資産の減価償却費が100,000円分発生した場合の仕訳方法の例は以下のようになります。
直接法の仕訳
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 減価償却費100,000円 | 備品100,000円 |
固定資産から直接差し引いて帳簿価額を表示させるため、帳簿上の資産の残存価値が常に最新の状態で表示できることから仕訳方法がシンプルでわかりやすい点がメリットとして挙げられます。
しかし、直接差し引くことで減価償却累計額は残らないため、費用の累積状況を追うにはすこし手間がかかってしまう点があります。
「間接法」での仕訳方法
間接法は減価償却費を「減価償却累計額」という勘定科目で計上し、固定資産から間接的に差し引く方法となります。毎月計上する減価償却費は積み上げられていくことが特徴といえます。
間接法の仕訳
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 減価償却費100,000円 | 減価償却累計額100,000円 |
貸借対照表では直接法とは異なり、取得価額と減価償却累計額が表示されるため、資産の取得原価と減価償却の累積情報を一目で把握できます。
資産の取得原価がそのまま残るため、比較や分析など資産評価をしやすいことから一般的にはこの間接法が採用されています。
一方、直接法と比較すると仕訳方法がやや複雑となり、固定資産の帳簿価額を把握するためには減価償却累計額を差し引く必要があるため、この手間においてはデメリットであるといえるでしょう。
減価償却費の勘定科目について
損益計算書では「減価償却費」として費用計上され、当期の利益を算定する際に直接影響しますが、賃借対照表では資産の帳簿価額を減額する形で計上されます。
- 損益計算書(PL)
→ 減価償却費は費用として「減価償却費」という勘定科目で計上
→ 当期の利益を計算する際に費用として差し引かれる - 賃借対照表(BS)
→ 減価償却費は費用なので直接BSには計上されない
→ ただし資産の帳簿価額が減る形で反映される
直接法:資産そのものの価額を減額
間接法:資産の控除勘定として「減価償却累計額」を使用
減価償却費を計算する際の注意点
前述では、定義や特徴、耐用年数や計算方法などについて触れてきました。 計算する際には法定で定められている償却方法に従い、適切な耐用年数で正確に計算することが大切です。
そのために注意したいポイントを以下で解説していきます。
法定の償却方法に従い適切な方法で行う
減価償却は、税法で定められた法定の償却方法を基本として計算する必要があります。
資産の種類や用途に応じて、定額法または定率法などが法令で指定されており、これに従わないと税務上認められない場合があるため必ず遵守しましょう。
主な税法上の取り決めは以下の通りです。
- ・ 資産ごとに認められる償却方法が決まっている
- ・ 耐用年数は固定資産の種類ごとに定められている
- ・ 残存価額は1円として計算される
なお、法定の償却方法と異なる方法を選択する場合は、所定の税務署への届け出が必要となります。届け出がない場合は計算方法が認められず、申告内容の修正や追徴課税の対象になることがあるため注意しましょう。
耐用年数は資産の種類に応じて正確に計算する
法定耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」により、資産の種類ごとに定められています。見落としやすいのが新品かあるいは中古かで耐用年数も変わるという点です。
誤った耐用年数で減価償却費を計算すると費用の過少・過大計上につながり、利益計算や税額計算に誤差が生じるリスクがあるため注意しましょう。
正しい耐用年数に基づく計算が、財務諸表の信頼性と税務適正の両方を確保するために重要です。
参考:減価償却資産の耐用年数等に関する省令|e-Gov 法令検索
減価償却費の計算には、ウェブ上で利用できる無料の計算ツールを使う方法もありますが、固定資産管理のシステムを利用することで、正確に計算・管理することができます。
また、クロノスが提供する経費精算システムは、操作しやすい画面設計で、パソコンやスマートフォンからかんたんに経費申請ができます。
申請者と承認者、経理管理者それぞれの業務を効率化する経費精算システムの詳細はこちら
まとめ
減価償却とは、取得した固定資産は長く使用するものと考え、費用を資産ごとに異なる耐用年数に応じて計上する会計処理のことです。
減価償却を計上する際は正しい耐用年数に基づいて計算し、法定で定められている償却方法に従うことが重要です。
クロノスの経費精算システムは、交通費申請を正確かつスムーズにすることができます。 領収書をスマートフォンアプリで撮影して申請画面へかんたんにアップロード、入力項目も自動で反映されるため経費申請と精算処理をスムーズにします。
精算申請では、勘定科目に紐づいた内訳を選ぶだけで自動的に仕訳されるため、従業員は該当する内訳名を選択するだけで済み、経理担当者の作業負担を大幅に軽減できます。
クロノスの経費精算が気になった方は「クロノス経費精算」をぜひご検討ください。
よくある質問
減価償却はどのタイミングで行う?
減価償却は以下のタイミングで行います。
- ・ 事業供用日の期から計上
- ・ 決算期ごとに計算・仕訳
- ・ 期の途中で取得した場合は月割計算で対応
法人は減価償却を任意に行えるって本当?
法人は税務申告上、減価償却方法を任意で選択可能ですが、以下の制限があります。
- ・ 法定の耐用年数に基づくこと
- ・ 法定の償却方法(定額法・定率法など)を遵守すること
個人事業主は強制償却が原則となります。