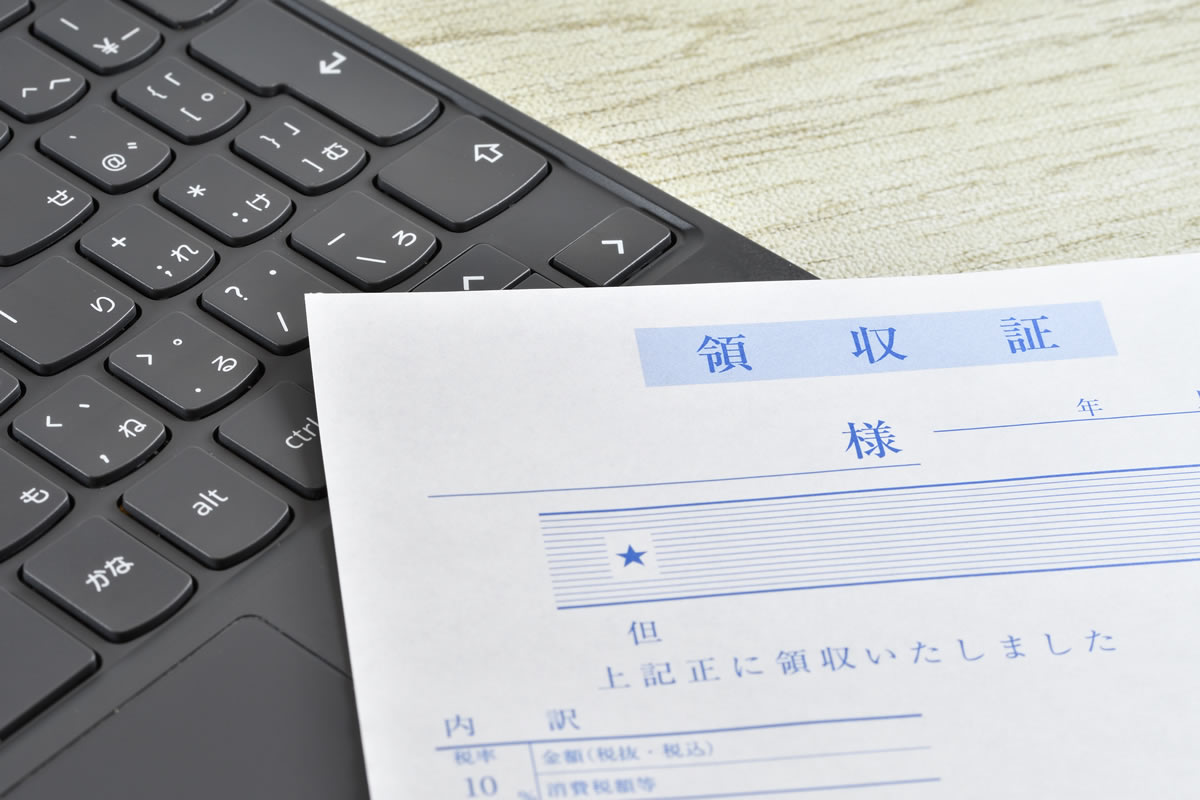クロノス広報チーム
経費精算は、従業員が業務に必要な支出を一時的に立て替え、後で会社がその経費を従業員へ払い戻すことです。
会社にとって欠かせない業務でありながら、手作業や Excel 管理では申請や承認に時間がかかり、さらには不正などのリスク発生も考えられます。
近年はクラウド型システムの活用によっての業務効率化やガバナンス強化が進み、従業員の負担軽減と経理部門の生産性向上を両立できるようになってきました。
では、実際どのように経費精算を進めればよいのでしょうか。
本記事では、経費精算の種類から費用、手順など、業務効率化を行うためのポイントについてわかりやすく解説していきます。
勤怠管理システムについて無料で見積もり・相談できます無料でお問い合わせ
経費精算とは何か?
経費精算とは、従業員が業務で立て替えた費用を会社が払い戻す手続きのことです。
交通費や出張時の旅費、接待費などが対象となり、領収書などの証憑を提出 → 上長・経理部門の承認 → 精算という流れが一般的となります。
企業活動において経費精算の適切な処理は非常に重要なため、正しく運用することで資金の流れが明確になり、税務処理の適正化や内部統制の強化にもつながります。
経費精算は企業にとって欠かせない重要な業務であり、正確性と透明性のある仕組みづくりが求められます。
経費精算の 3つの種類
経費精算の種類は主に 3 つ、下記に分類されます。
- 小口精算 :少額の備品購入や消耗品など
- 交通費精算:電車・バス・タクシーなどの移動費
- 旅費精算 :出張に伴う宿泊費や日当など
目的によりどの経費精算が該当するのか、やり方やポイントを解説していきます。
小口精算
小口精算とは、備品や消耗品など日常業務の中で比較的少額かつ頻繁に支出する経費において、一時的に小口現金を使って立て替える精算方法です。現金出納長で、現金の出入りを管理します。
小口現金…企業が発生した経費のため手元に用意する精算用の現金
キャッシュレス化によって小口精算の縮小は進んでいますが、管理を行う場合は不正防止や管理負担を軽減させるため、利用ルールを明確にすることが大切といえます。
また、従業員は申請時に必ず領収書を添付し、企業によって任意で定められた金額の上限を超えないよう注意が必要です。
交通費精算
交通費精算とは、業務に伴う交通費を従業員が申請し、会社が払い戻す精算方法です。
訪問先への電車・バス代やタクシー代が対象となり、最近では IC カードの利用履歴を活用してより正確に精算する方法も注目されています。
また、自家用車を利用した場合は走行距離に基づき社内規定の単価で精算することが一般的となり、下記の計算方法で精算されます。
移動距離×企業で定められた 1kmあたりの距離単価
申請の際には移動距離や金額を明確にし、領収書の添付を必ず忘れないようにしてください。
旅費精算
旅費精算とは、出張時に発生する交通費や宿泊費などの旅費を会社へ申請し、精算する方法です。新幹線や飛行機での移動費、ホテル宿泊費に加え食費や雑費を補う日当も規程に基づいて支給されます。
特に旅費精算においては、横領罪となるカラ出張など不正リスクへの注意が必要です。
このリスクを回避するためにも、経理担当者は旅費精算時に 「誰が・いつ・どこで何をしたのか」といった勤怠の情報を併せて把握し、管理しなければなりません。
また、従業員は旅費精算においても申請の際には領収書の添付が欠かせません。企業ごとに定められた旅費規程を事前に把握したうえで、申請することが大切です。
経費精算の対象になる費用
以下は経費精算の対象となる 4 つの費用です。
- 1. 旅費交通費
- 2. 交際費・会議費
- 3. 消耗品費
- 4. 福利厚生費
企業が負担すべき一般的なそれぞれの費用について解説していきます。
1.旅費交通費
旅費交通費は、従業員の出張時にともなう勤務地から別の場所へ移動した際に発生した交通費と、宿泊費や日当手当を計上するための勘定科目です。
経費精算の中でも比較的申請件数が多くなりがちなこの費用では、私的利用と業務利用を分けて申請することが求められます。
不正リスクを防ぐためにも、何の目的で発生した出張なのかを明確することが重要です。
申請時に領収書を添付することはもちろんですが、新幹線代においては経路や利用区間を明確に記録することが大切です。たとえば「東京―新大阪」などの区間や利用日、グリーン車を利用したのかどうかを把握できると、経理担当者も安心して承認できるでしょう。
多額となりやすい費用を従業員が一時的に立て替えるため、申請側にとっては“はやく処理したいもの”ですが、経理担当者は“正確さ”が欠かせない部分です。
近年は予約サイトから手軽に領収書を発行できるケースもあるため、申請時には必ず領収書を添付し、利用区間や宿泊先などの詳細を記載したうえで申請してください。
2. 交際費・会議費
交際費は、取引先や顧客との関係を築くために発生した飲食代や、接待、贈答品などを計上する勘定科目です。
例えば商談後の会食や手土産、お歳暮などがこれにあたります。
会議費とは、社内会議や社外で会議を行う際にかかる費用を計上する勘定科目となり、社内会議や社外の取引先と会議をした場合など、ビジネス運営を行ううえで発生する費用を指します。
この会議費においては、社外での打ち合わせにともなう軽食やカフェ代など、業務上必要な場面に限られる点がポイントです。
会議費として計上できる“一人あたり 10,000 円基準”とは、会議費として処理できるか交際費とするかの分かれ目となり、これを上回る場合は原則として交際費として扱う必要があります。
また、令和 6 年度の税制改正により、交際費の損金算入特例は 3 年延長となりました。
中小法人は、交際費等の 800 万円までの損金算入と飲食費の 50%相当額の損金算入とのいずれかを選択することができます。(措法 61 の4①②)
税務上の取扱いに影響するため、経理処理をおいてはこれらの費用を区別し、正確かつ適切な勘定科目で処理を行う必要があります。
3.消耗品費
消耗品費は、業務に必要な文房具や事務用品など消耗品にかかる費用を計上する勘定科目です。例えば社内で頻繁に使用する、コピー用紙、ボールペン、ノート、ファイルといった日常的に使用する物品が該当します。
原則として取得価格が 10 万円未満の物品であれば消耗品費に計上でき、これを超えるパソコンやシュレッダーなど高額な備品は固定資産として扱われます。
この消耗品費の処理で混同しやすいのが、「消耗品」と「雑費」の区分です。
消耗品費は文房具やプリンターインクなど、業務で繰り返し使う物品が中心なことに対し、雑費はいずれの勘定科目にも当てはまりにくい少額支出の受け皿となります。
実務では「とりあえずの雑費」で片付けると経理上の透明性が下がるため、できる限り消耗品費や他の科目に仕分けることが望ましいでしょう。
4.福利厚生費
福利厚生費は、従業員の健康を守りながら働きやすい環境を整えるために会社が支出する費用を指す勘定科目です。
福利厚生の内容は企業ごとに異なりますが、その条件を確認したうえで就職活動や転職活動を行うなど、従業員にとっては働くモチベーションに直結する重要な要素となります。
しかし、この福利厚生費は内訳や計上するための条件が複雑であることや、法律により定められているものと会社独自で定めているものがあるため、平等性や金額の妥当性などの条件を満たし、適切な区別を行うことが大切なポイントです。
代表的なものには慶弔見舞金や健康診断の費用、社内レクリエーションの開催費という内訳があります。この費用は従業員全体や一定の条件を満たす人に公平に提供される必要があるため、一部の従業員だけのための費用は福利厚生費として認められません。
福利厚生費は「社内の従業員のため」に使われる費用であることが重要です。
こうした制度の目的を理解しながら課税か非課税対象となるかという点や、内訳の整理と条件を確認し、適切に処理する必要があります。
1. 経費精算の手順
経費精算の流れでは従業員と経理担当者それぞれの立場で行う内容が異なります。
- STEP 1 立替払いをする(従業員)
- STEP 2 領収書を受け取り保管しておく(従業員)
- STEP 3 経費精算書を作成し、経理に提出する(従業員)
- STEP 4 立替費用を払い戻す(経理担当者)
経費精算の方法は会社によって異なりますが、順を追って一般的な流れを整理していきましょう。
STEP 1 立替払いをする(従業員)
従業員が業務に必要な費用を所持金から立て替えで支払います。ここでまず大切なのは、業務との関連性が明確に説明できることです。
私的な支出や交際費と誤解されるものは精算対象外となるため、注意が必要です。
社内ルールに見合った申請ではない場合や、プライベートと混合してしまっていると承認を得られず経理担当者との差し戻しが発生するなど、双方で手間がかかってしまいます。
出張や会議費など具体的な利用目的をもつことがポイントです。
また、支払いの方法は現金で払うよりも、できればクレジットカードや会社指定のキャッシュレスを利用すれば記録が残るため、紛失した場合や何かの証明が必要となった場合、支出の事実を証明する資料となります。
現金払いになる場合も、必ずその場でレシートや領収書をもらって保管しておきましょう。
STEP 2 領収書を受け取り保管しておく(従業員)
次に、経費精算で必ず必要となるのが領収書です。
立て替えたら発行された領収書を受け取り、会社から払い戻しがあるまで大切に保管しましょう。
また、領収書には発行日 ・宛名・金額 ・発行先・但し書きが正しく記載されている必要があります。特に但し書きが「お品代」など曖昧な場合、業務関連性を証明しにくくなるため、できるだけ具体的に記載してもらうことが望ましいです。
保管方法は紙のままでも構いませんが、現在は電子帳簿保存法に基づき電子データとして保存するケースも増えています。
スマートフォンで撮影した領収書や PDF をシステムにアップロードする形であれば領収書を探す手間などを削減し、社内での効率化が図れるため推奨されつつあります。
STEP 3 経費精算書を作成し、経理に提出する(従業員)
領収書を準備したら、次は経費精算書を作成して経理部門に提出します。
経理担当者のもとへ届くまでに、上長が業務との関連性や金額の妥当性を確認し、適切な費用であると承認することが必要です。
また、経費精算書の作成時は社内ルールに従って日付、利用内容、金額、勘定科目、支払方法といった必須項目を記載し、立て替え証明となる領収書をつけるのが基本です。
紙の様式を利用する会社もありますが、最近では Excel テンプレートや経費精算システムを導入している企業が多く、入力すると自動で勘定科目が振り分けられる仕組みが整っています。
アプリから領収書をアップロードし、電子データをそのまま添付できるためスムーズに効率化を図れる点が、経理部門側の処理負担軽減にもつながるでしょう。
STEP 4 立替費用を払い戻す(経理担当者)
経理部門のもとへ提出された承認済みの経費精算書を基に、従業員へ費用が払い戻されます。
多くの企業では、経費精算の振込は月に数回まとめて行われるケースが一般的で、例えば「月末締め・翌月 10 日払い」「毎週金曜に処理」「給与振込と同じタイミングで払い戻し」といったスケジュールが設定されています。
振込前には、金額や口座情報に誤りがないか最終確認を行うことが重要です。
フローがしっかりとルール化されていればチェックミスを減らせ、従業員への支払い遅延も防ぐことができるでしょう。
領収書と経費精算書に書かれた金額が一致しているか、費用が会社規程に基づいているかなど、最終確認のポイントを押さえておくことも大切です。
経費精算で領収書が必要な理由とは
経費精算では領収書の提出が必ず必要となります。
ではなぜ領収書が必要なのか、3 つの理由について解説していきます。
- 業務に関連した費用か確認するため
- 二重払いのリスク防止のため
- 虚偽申告をしていないか確認するため
業務に関連した費用か確認するため
経費精算において領収書は、経費申請で提出したその支出が業務に必要だったことを裏付ける最も基本的な証拠となります。
出張の交通費や取引先との会食費など、業務上での必要性があるかどうかは日付や利用内容が記載された領収書で確認されるため、もし領収書がなければ私的な支出との区別が難しくなり、経理担当者が正確な処理として扱うことができません。
また、税務調査の際には支出の妥当性を証明する書類が求められるため、領収書は企業にとって欠かせない存在です。
二重払いのリスク防止のため
日々発生する費用においては、二重払いとなるリスクを未然に防止しなければなりません。
領収書を提出することで似た内容の経費が重複して申請される可能性があるため、領収書がある場合にのみ処理を行う運用ルールであれば、誤った金額で払い戻ししてしまうといったことや同じ内容に二度帳簿に付けてしまうといったリスクも減らせます。
こうしたミスや不正を防ぐため、領収書番号や発行日付、金額をチェックして正確性の高い処理が求められます。
虚偽申告をしていないか確認するため
領収書は、経費申請の虚偽申告などの不正を防ぐためにも重要な役割を果たします。
例えば、私的な飲食費や買い物を「業務上の支出」として申請してしまうケースを防ぐには、日付や支払先、金額が記載された領収書の確認が不可欠です。
経理担当者がこれを精査することで、虚偽申告を抑止し、社内の信頼性を保つことができます。
さらに、税務調査が行われた場合でも、支出が領収書に基づき適切に処理されていることを根拠として示し、財務管理においての正確性も保つことができます。
領収書を正しく管理することは内部統制の強化にもつながり、会社全体のコンプライアンス体制を支える重要な仕組みもといえるでしょう。
経費精算を効率的に行うためのポイント
経費精算を効率的に行うためには、次の 2 つを押さえていきます。
- 経費精算システムを導入する
- 経費精算の社内ルールを決めておく
この 2 つは経理業務の効率化と正確性を図るポイントとなるので、参考にしてください。
経費精算システムを導入する
経費精算業務を効率化させるには、まず経費精算システムの導入をおすすめします。
経費精算システムは規程のマニュアルに沿って設定を行うだけで、意外にも簡単に操作ができてしまうという点が魅力のひとつです。
導入することで、申請から承認、支払いまでの一連の流れを効率化できるというメリットはもちろん、従業員はスマートフォンや PC から領収書を撮影・添付して申請できるので、紙の書類を回覧する手間や紛失リスクがなくなります。
会計ソフトと連携できるシステムであれば、会計業務全体の効率化を図れるため、経理処理の負担を大幅に軽減できます。
導入を検討する際は、自社の業務規模や利用頻度、痒い所に手が届くシステムであるかを基準に選定することが大切です。
細かい機能で言うと、「交通系 IC カード連携」や「承認フローのカスタマイズ」といった、自社に必要な機能などが挙げられます。
料金体系も月額制や従量課金制などさまざまなので、純粋に使いやすいかといった点を含めながら費用対効果を踏まえて選定しましょう。
経費精算の社内ルールを決めておく
効率的な経費精算を行うためには、社内ルールを明確化しておくことが欠かせません。
「費用として認められる対象や上限金額」「出張費は帰社後 1 週間以内に申請」「承認は課長以上が行う」ことや、「高額な申請となる場合は事前申請を行う」など、申請期限や承認フローを具体的に定めておくことで、差し戻しや確認作業が減り、処理がスムーズになります。
申請対象となる費用の範囲を明確にすることで、従業員が迷わず申請でき、不必要な問い合わせを防ぐ効果もあります。
この社内フローが明確になっておらず社内への周知も十分でない場合、管理が煩雑化し処理方法が統一されないことでミスが発生する恐れがあるため、一貫した運用を徹底することが重要です。
まとめ
経費精算は、従業員の立替払いを正しく払い戻すと同時に、企業全体の資金管理や内部統制に直結する重要な業務です。
日々発生する経費は、種類に応じて適切な勘定科目で正確かつミスなく処理する必要があります。
経費として計上できる税金やそうでないものがあるなど管理項目は多岐にわたり、紙の領収書管理では手間がかかるため、システム化を望む経理担当者も少なくありません。
クロノスが提供する経費精算システムは、操作しやすい画面設計で、申請状況や対応すべき内容をダッシュボードから一目で確認でき、経理業務を正確かつスムーズに進められます。
さらにクロノスの勤怠管理システムと連携することで、管理が煩雑化しやすく経費処理のミスが起こりやすいといわれている旅費精算も、勤怠の情報と紐づけて管理できるため不正リスクの防止にもつながります。
クロノスの経費精算が気になった方は「クロノス経費精算」をぜひご検討ください。
よくある質問
レシートのみでも経費精算できますか?
レシートでも経費精算は可能です。ただし、支払先や金額、日付など必要な情報が明確に記載されていることが条件となります。
経費精算は何が対象ですか?
経費精算の対象は、旅費交通費、交際費、消耗品費、福利厚生費など。業務に必要で会社規程に沿った支出が対象となります。